最新ニュース
主要生成AIサービスの学習データと最新情報アクセス能力
2025年7月1日時点での主要生成AIサービスの学習データ「カットオフ」に関する調査結果が公開されました。調査によると、各サービスやモデルで学習データの最終更新時期には違いが見られます。例えば、Geminiは2024年6月まで、ChatGPTのGPT-4 Turboモデルは2023年10月までのデータを学習済みとされています。Grokは概ね2024年6月まで、Copilotはモデルにより2024年6月から2025年7月1日までの範囲で学習データが更新されていると回答しました。多くのAIサービスに共通するのは、学習データが特定の時期までであっても、それ以降の最新情報についてはウェブ検索機能を通じてリアルタイムにアクセスし、回答に反映させることが可能であるという点です。これにより、ユーザーは過去の学習データだけでなく、現在の状況に関する情報も得られると期待されます。記事では、Grokのリアルタイム情報収集能力に触れつつ、最近の回答精度に課題が見られる可能性を指摘し、対照的にChatGPTの進化に注目が集まっているとのことです。
引用元:emiaoki.net

U-22 プログラミング・コンテスト2025、コード生成AIの活用を正式許可
U-22 プログラミング・コンテスト2025の応募受付が、2025年7月1日より開始されました。このコンテストは、若手プログラマーやクリエイターがアイデアをプログラミング技術で実装し、世の中をより便利に、そして楽しくする作品を募集しています。特筆すべきは、今年から作品制作過程におけるコード生成AIの活用が正式に認められた点です。単にAIを利用するだけでなく、これまでにない新しい活用手法を見出すなど、独創性や新規性が評価される場合、あるいは実装に高度な技術力を要する場合には、加点要素となる可能性があります。一方で、コード生成AIを利用しつつも、プロンプトの指示やリファクタリングが不十分でデッドコードが多く含まれる作品は、減点につながる可能性も示唆されており、参加者にはAIを単なるツールとしてだけでなく、自身の創造性や技術力を高めるためのパートナーとして活用することが求められます。
引用元:gihyo.jp
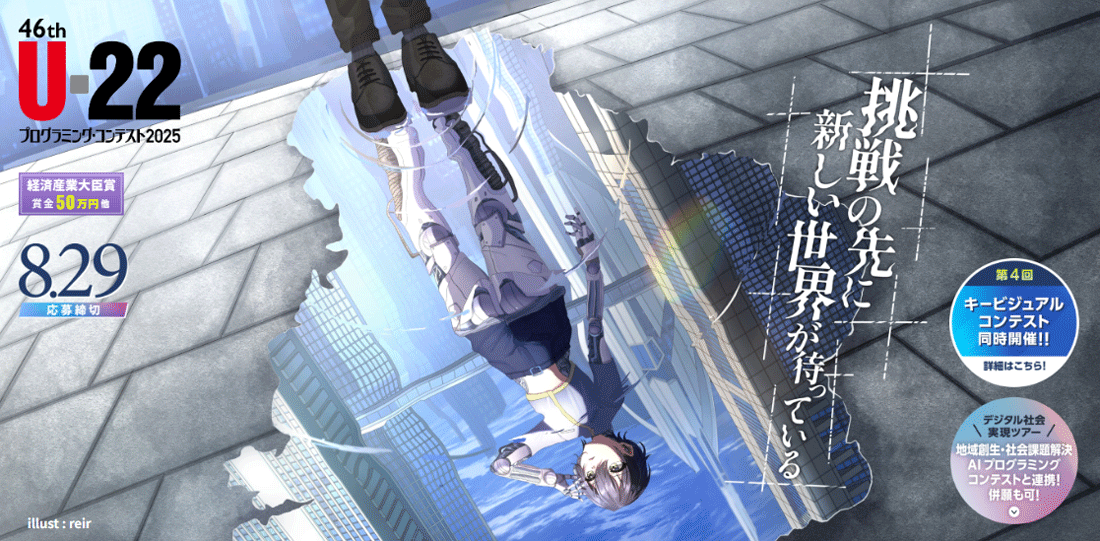
Google Gemini、メッセージアプリへのアクセス権限拡大とプライバシー懸念
GoogleのAI「Gemini」が、メッセージアプリや通話機能など、スマートフォンの主要機能へアクセス可能になる仕様変更が2025年7月7日から適用されると報じられました。近年注目される「エージェンティックAI」は、ユーザーの代わりに自律的に行動・実行するAIを指し、その利便性が期待される一方で、支払い情報やプライベート情報といった個人情報へのアクセスが不可欠となります。今回の変更では、「Geminiアプリのアクティビティ」の設定に関わらず、Geminiがこれらの機能にアクセス権を持つ可能性があるとされており、一部Androidユーザーに送られたGoogleからのメール内容が懸念を呼んでいます。特に、機能のオフ設定方法が不明瞭な点や、アクティビティが有効な場合には利用情報が最大72時間保存され、一部データが人間によってレビューされる可能性がある点が指摘されています。Google広報は、今回のアップデートはユーザーにとって有益であり、オフ設定ではやり取りがレビューされたりモデル改善に使用されたりすることはないとし、接続はいつでもオフにできると案内しています。記事は、AIがスマートフォンに統合される中で、ユーザー自身がデータの取り扱いについて理解し、冷静に判断する必要があると結んでいます。
引用元:dメニューニュース

プレスリリース
メタリアル・グループ、証券営業向けAIエージェント「Metarealセールス」提供開始
株式会社メタリアルグループの株式会社ロゼッタは、証券営業向けの新たなAIエージェント「Metarealセールス(Metareal SL)」の提供を2025年7月1日に開始しました。Metareal SLは、顧客ポートフォリオ分析レポートを自動で作成するAIアナリストです。証券会社の営業担当者が顧客ごとの資産構成やパフォーマンス、リスク指標、投資傾向を自動分析し、提案内容と連動したレポートを数分で生成可能です。これにより、顧客一人ひとりに合わせたタイムリーな提案が可能となり、属人化しがちな営業現場での課題解決に貢献することが期待されます。主な特徴として、顧客資産データの自動取り込みと即時分析、AIによる最適な提案方向性の提示、PDF/Word形式でのレポート出力、推奨アクションの提案が挙げられています。同社は今後、金融業界に限らず様々な業種に特化した生成AIシリーズ「Metareal AI」を展開し、AIコンサルティングサービスを強化する方針です。
引用元:PR TIMES

イグアスとNDIソリューションズ、生成AI×動画解析ツール『Video Questor』で提携
株式会社イグアスは2025年7月1日より、NDIソリューションズ株式会社が開発・提供する生成AI×動画解析ツール『Video Questor』の代理店販売を開始すると発表しました。『Video Questor』は、動画をアップロードするだけでAIが自動的に内容を解析し、ユーザーがチャット形式で入力した質問や指示に応答する画期的なツールです。動画の要約、質疑応答、マニュアル作成、翻訳などを瞬時に行い、従来の動画視聴方法を一変させることで、業務効率と生産性の飛躍的な向上が期待されます。イグアス社は、本製品の販売開始に先立ち社内検証を実施。その結果、あらゆる業務・業種において十分な有効性が認められ、会議や研修の議事録作成、社内マニュアル作成、営業活動の効率化、顧客対応の品質向上といった領域で効果が確認され、社内導入に至っています。両社は今回のパートナーシップを通じて、『Video Questor』の価値を広げ、多くの企業のデジタル変革と新たな価値創出を支援していく姿勢を示しています。
引用元:株式会社イグアス

利活用系記事
筑波銀行が全職員向けに生成AI「ChatGPT」を本格活用開始
筑波銀行は2025年7月1日より、全職員を対象とした生成AI「ChatGPT」の本格的な活用を開始しました。これは、生産性向上と業務効率化を目指し、同行専用環境「つくばChatGPT」を導入したものです。同行は本導入に先立ち、2025年2月から本部・営業店の一部で「ChatGPT」のトライアル運用を実施していました。今回の全職員への対象拡大は、情報セキュリティを確保しつつ、業務デジタル化効果の一層の向上を目指しています。活用用途は幅広く、資料作成、文書要約、文書案作成、翻訳、アイデア出し、マクロ作成、簡易プログラミングなどが挙げられています。これにより、行内業務を効率化し、捻出された時間を顧客相談や企画業務に充当することで、生産性向上に繋げることが期待できるとのことです。本施策は、同行が掲げる第6次中期経営計画「Rising Innovation 2028」における「TXデザイン」の一環であり、今後も高度なAI活用を検討し、デジタル化を促進することで、銀行業務の高度化と質の高いサービス提供を目指すとのことです。
引用元:筑波銀行
ネットイヤーグループ、「生成AIに全振り宣言」で事業戦略を転換
ネットイヤーグループは、急速に進化する生成AIに対し「すべての経営資源を生成AIに振る」と宣言し、事業戦略の軸足を移しています。この取り組みを加速するため、エンジェル投資家の川崎裕一氏を生成AI推進担当顧問として招聘しました。廣中社長は、検索行動の変化と業界の将来に対する危機感から、インターネット黎明期に匹敵する生成AIの波に乗る必要性を強調しています。川崎氏は、現在の生成AI活用が企業にとって当たり前であり、推論コストの劇的な低下から、活用しない企業は競合に太刀打ちできない現状を指摘しました。ネットイヤーグループは、長年培ってきたユーザーエクスペリエンス(UX)を捨てるのではなく、生成AIをアドオンすることで、顧客にとって便利かつ信頼できるAIエージェントを提供し、差別化を図る方針です。先日開催された社内での生成AI活用事例発表会では、ホテル業の問い合わせ対応や行政機関のパブリックコメント振り分けなど、具体的な事例が多数紹介されました。同社が提唱する「ABAC(AI agent-Based Autonomous Communication)モデル」は、企業側と個人側のAIエージェント同士が自律的に会話し、リアルタイムでユーザーの要望に応える未来を描いています。
引用元:沖縄タイムス+プラス

Renewerが「生成AI × 図解術ガイドブック 2025」を公開
Renewerは2月28日、ビジネスパーソン向けに、生成AIを活用して効果的な図解を行うためのTips集「生成AI × 図解術ガイドブック 2025」を公開しました。AI技術の急速な進化により、単なる文章生成だけでなく、画像や動画などのビジュアル表現も高精度で生み出せるようになっています。ビジネスシーンで最も活用されているビジュアル表現の一つである「図解」は、物事を視覚的に整理し、思考を深め、情報を分かりやすく伝える優れた手段とされています。しかし、多くの人が「自分の考えを図で表現するのは難しい」と感じており、生成AIはこうした図解の分野において強力なツールとなり、これまでよりも簡単に活用できるようになりつつあります。このガイドブックは40ページ以上にわたり、図解に使う素材収集から、図表・グラフ・イラストの作成までをまとめた「総合」パートに加え、資料作成、整理・分析業務、学習・教育、ソフトウェア開発におけるエンジニアリングやデザインなど、多様な場面での活用法を紹介しています。また、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、NapkinAI、Miroなど、図解に活用できる多彩な生成AIサービスや最新モデルを取り入れた効果的な図解方法も解説されています。同社は、生成AIを活用して「人の能力を高める方法」を分かりやすくまとめることを目指す「生成AI × アップスキリング」シリーズの一環として、ビジネスパーソンのスキルアップを支援する目的で本ガイドブックを作成しました。
引用元:ProductZine
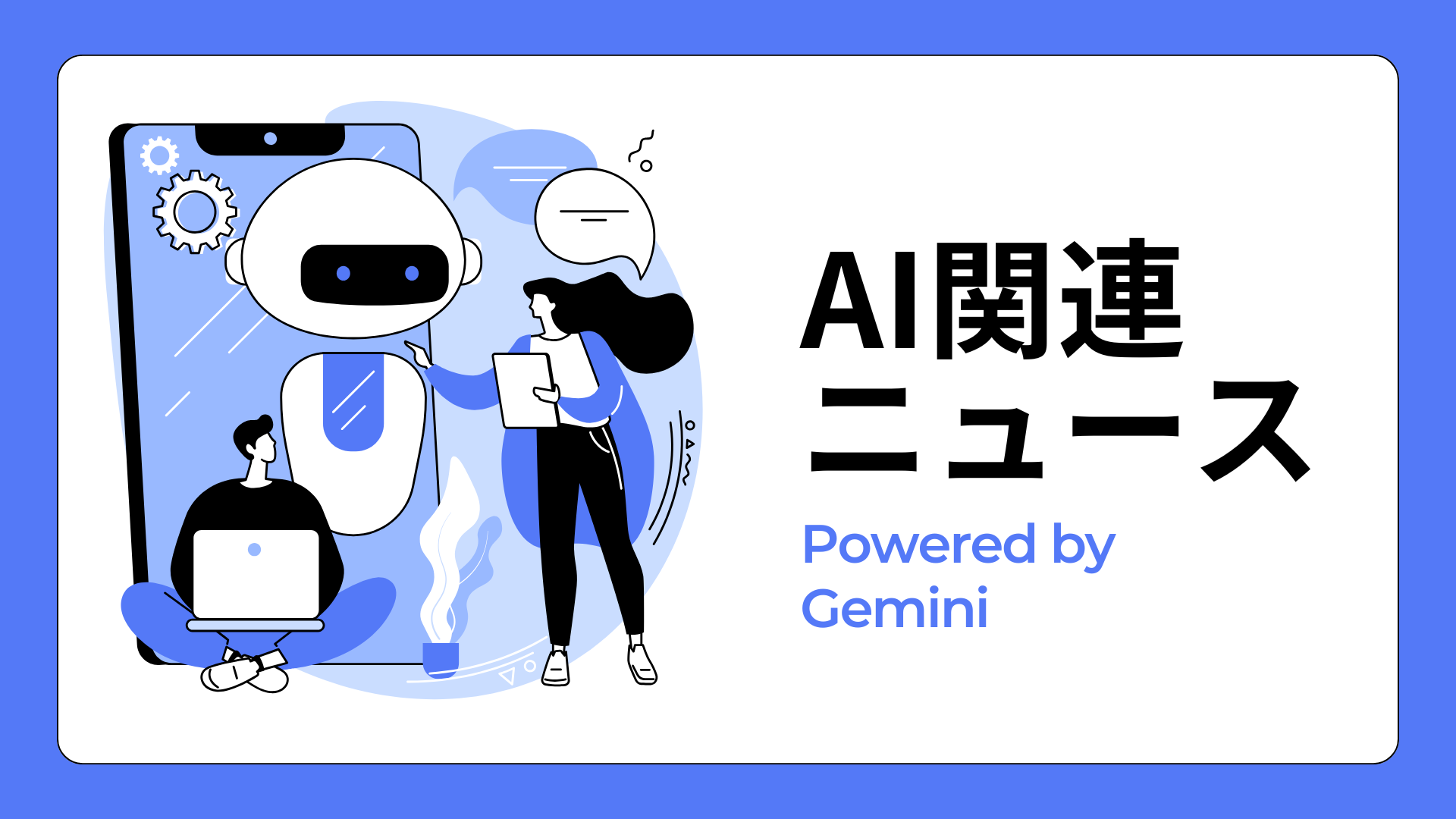

コメント